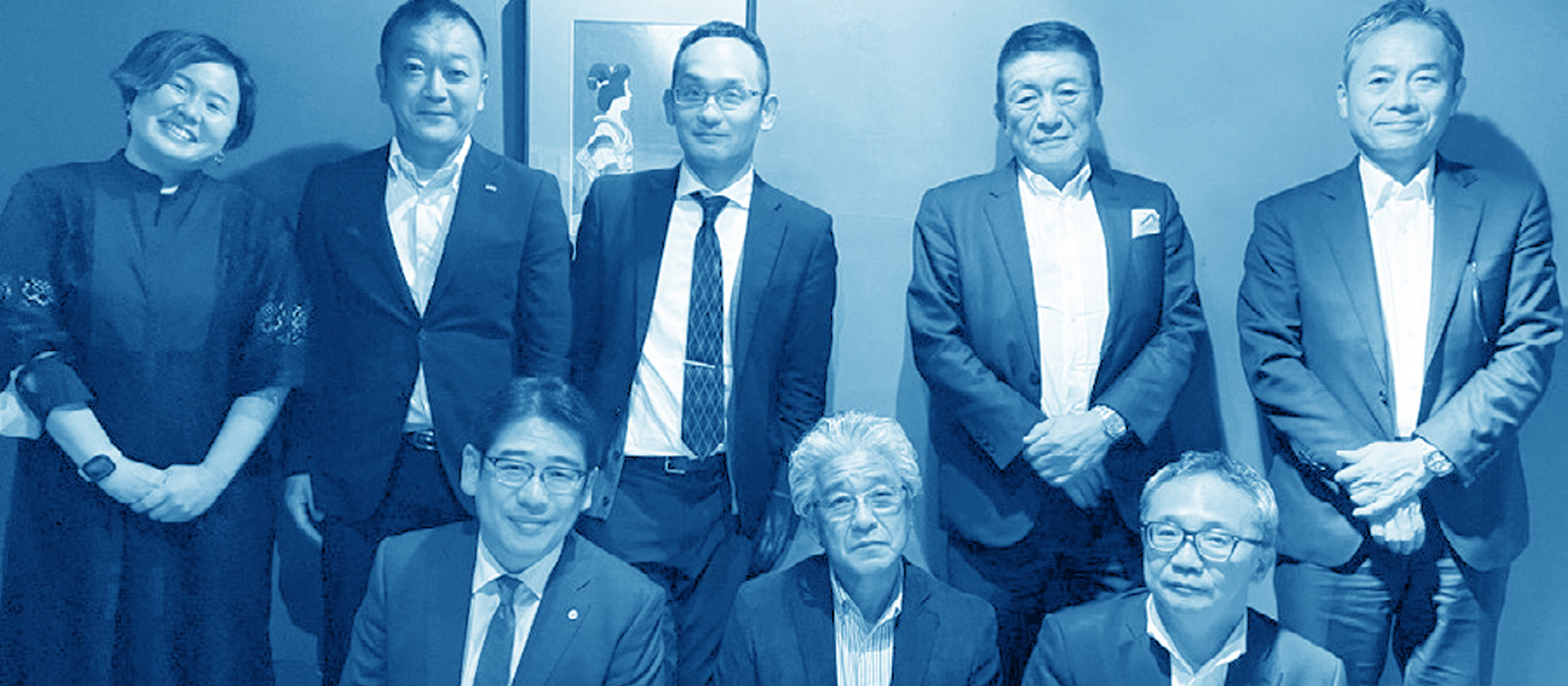
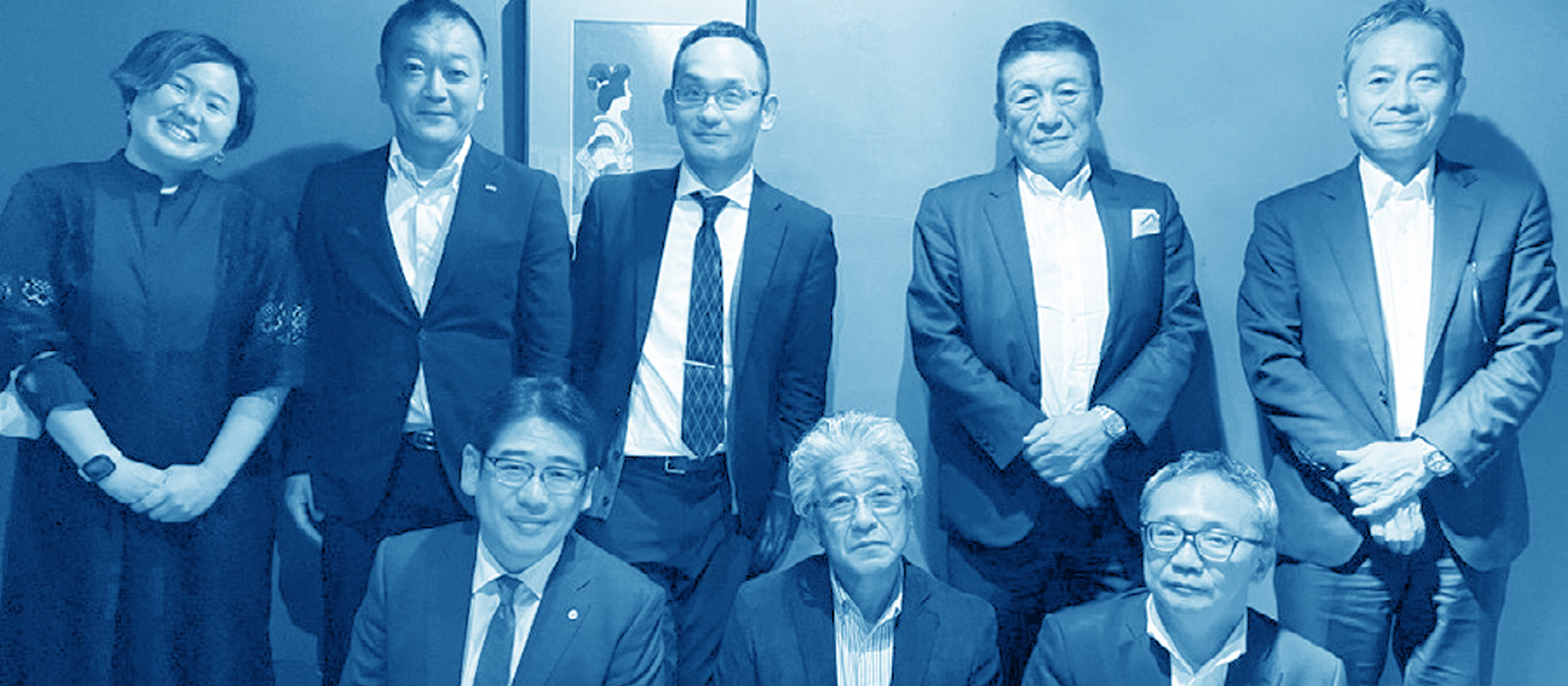
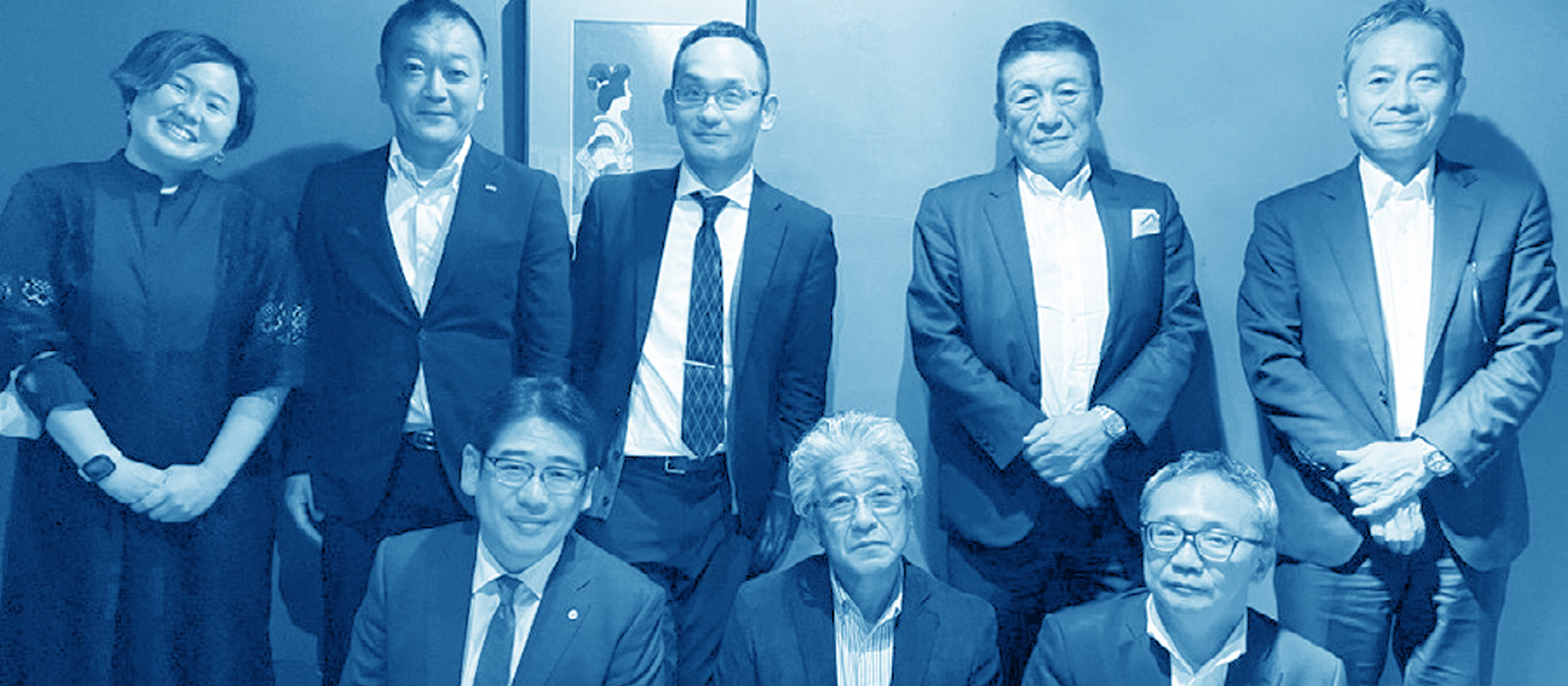
今年も開催されるC&D JAPAN2025は2025年9月から2026年5月末日まで当組合のHPにて開催されます。今回は開催に先立ち特別企画として当組合の下村理事長を囲み、賛助会員各メーカー代表との座談会を企画しました。業界の現状、問題点から、当組合の活動状況、各メーカーのものつくりに対する思い、C&D JAPAN2025についてなど多岐にわたる内容となりました。
この座談会を通じて、業界、ダイヤモンド工事業協同組合、各メーカーを少しでもご理解、ご興味を頂き、当組合員が使用している機材、ダイヤモンドツールの最新製品が展示されるC&D JAPAN2025により多くの方々がご来場いただける事を願っております。
|
座談会名 |
「下村理事長と賛助会員メーカーにて私たちの業界を語る」 |
|---|---|
|
開催日時 |
令和7年6月10日 |
|
開催場所 |
組合事務局 |
| 出席者 |
|

建設・解体業界、特にダイヤモンド工事業界は、深刻な人材不足とそれに伴う複合的な課題に直面しており、これは、単なる労働力の不足に留まらず、業界全体の持続可能性に関わる根深い問題である。
「仕事はあるけど、人が足らない状況が向こう10年20年もっと増えてくるのかな?なぜなら、作業に携わる担い手がいなくなるので。」という声は、業界の切迫した状況を表しています。この人手不足は、「倍とか三倍の話じゃなくて、2乗4乗の形で」悪化するとの認識があり、これは少子高齢化による労働人口全体の減少に加え、若年層の建設業離れ、特に過酷なイメージが先行するダイヤモンド工事業界への参入障壁が高いことが背景にあります。

熟練の技術者が引退を迎えつつある一方で、「若い人たちがどうやって来るか」という問いは、技術と経験の円滑な「伝承」が困難になっている現状を浮き彫りにしています。「若い子がいないっていうところは各会社一定の悩みとしてはある。昔は向こう5年、10年、弟子入り、で一人前になっていってというようなのを待てるような時代だったのかなとは思うのですけど、今そこでどうしても若い子がやめてしまう。
早ければ一年二年でやめてしまうというところを考えると。」という発言は、若手人材の早期離職が深刻な問題であり、かつての徒弟制度のような長期的な育成モデルが機能しにくくなっている現実を表してします。この傾向は、技術の継承を阻害し、将来的な生産能力の低下などの懸念となります。
「要はもう人件費を確保していかないと潰れていく、価格に転嫁できないところは必ず潰れていく。」という危機感は、業界全体で共有されています。これは、労働者にとって魅力的な賃金を確保し、企業の存続と成長を両立させるために不可欠な事。過去の過度な単価競争が企業の体力を奪ってきた教訓から、「業界全体に適正単価を取れるようにしていかないと」という意見は、適正な利益率を確保し、それを人件費や教育投資、設備投資に回すことで、業界全体の質を向上させようとする強い意志の表れです。
特に下請け業者の立場が弱い現状に対し、「元請けっていうのは下請け守れよっていうぐらいの気持ちで」接するべきとの提言は、サプライチェーン全体での公平な利益配分と共存共栄の重要性を訴えています。一方で、「今単価競争の話をするお客さんが少ないのですよ。昔はね、5センチがいくらだ、そこがいくらだって。今、お客様が単価競争の話をすることが少ないので。ある意味ではお客様自身が上げられてきているのかなと。そういう意味でとても安心しております。」という発言は、発注者側も業界の現状を理解し、適正な対価を支払う方向へシフトしているというポジティブな変化を示しており、これは業界にとって大きな安心材料となっています。

国土交通省からも「極力省力化、無人化を目指してくれませんか?」と求められているように、限られた人材で効率的に作業を進めるための自動化・省力化は喫緊の課題です。「2人でやるところを1人。例えば1週間かかるところを3日でとか、そういうことが我々に求められるテーマ。」と、生産性向上が明確な目標とされています。

しかし、コンクリートカッターのような大型機械は、現場の複雑性や安全性の確保が難しいため、「実際コンクリートカッターの場合、多分自動化はあの大きさでは不可能だと思います。」という現実的な見方も示されています。完全に無人化するのではなく、いかに人間の負担を減らし、効率を高めるかが焦点となります。
メーカー側は、少子化の日本において「ある一定のパフォーマンスがすぐできるものっていうのを開発していかなきゃいけない。」と考えており、例えば、機械の軽量化や操作アシスト機能の導入を通じて、これまで体力的に難しかった女性や高齢者でも安全かつ容易に扱える機械の開発を目指しています。これにより、労働力供給の多様化と確保に貢献することが期待されています。
建設・解体業界は「達成感が少ない」と見られがちで、これが若い世代への認知度低下に繋がっています。「切ったり、穴開けたり壊したりするものに関しては、結果が目に見えず維持されて出てこないから、達成感がないのか、イコール認知度も広がっていかないし。」という指摘は、新築建築物のような形として残る成果が見えにくいことが、業界の魅力を伝えにくい一因であることを示しています。
この現状を打破し、「若い人に認知度が少ないのはどんな仕事を行っているのかがわかんないからね。」という課題を解決するため、「カッター屋物語みたいなアニメ作ってほしい。」といった具体的な提案も出ました。これは、エンターテイメントを通じて業界の仕事内容や魅力を分かりやすく伝え、興味を持ってもらうための斬新なアプローチです。さらに、「我々が行っていることがライフラインを支えることでこの社会を支えているってことをもっとアピールすべきだ。」と、インフラ整備や維持管理という建設業の根幹を支える社会貢献性を積極的に発信し、誇りを持てる仕事であることを強調していく重要性が繰り返し発言されていました。
業界が直面する課題は大きいものの、座談会参加者からは、ダイヤモンド工事業界の将来に対する非常に強いポジティブな見通しが示されています。これは、業界の基盤となる仕事の性質と、DCA(ダイヤモンド工事業協同組合)の積極的な活動に裏打ちされています。
「我々の業界は、まず仕事は絶対になくならないと思っている。」という確信は、ダイヤモンド工事業の根本的な必要性に基づいています。インフラや社会資本が存在し続ける限り、この仕事は必要不可欠です。

具体的な例としては、「新築だ、開発だって言いますが、やはり老朽化していく。それも、また50年後に老朽化していく。ずっと同じサイクルなので、まあ延々となくならないです。絶対。」と語られているように、高度経済成長期に建設されたインフラの老朽化が急速に進んでおり、その維持管理、修繕、そして更新は今後も継続的に発生します。
橋梁、トンネル、高層ビル、そして特にこれまで手薄だった「下水道などの維持管理」が今後極めて重要になると指摘されており、これは新たな仕事の需要を意味しています。ダイヤモンド工法は、精密な切断・解体技術として、これらの既存インフラの維持管理において代替の効かない役割を担うため、仕事がなくなる心配はないという強い自信があります。
座談会で強く打ち出された理念が、「今後は少ないパイを奪い合う時代から必ず分け合う時代、シェアする時代になるので、高くていい単価の仕事をみんなで分け合う。そうして、みんながハッピーになる。」というものです。これは、限られたパイを奪い合うのではなく、業界全体で適正な利益を確保し、その利益を会員間で分かち合うことで、全ての企業が健全に成長し、労働者も適正な対価を得られる社会を目指すものです。
この「シェアする時代」への移行は、価格競争から価値競争への転換を意味し、結果として業界全体の品質向上、技術革新の促進、そして労働環境の改善に繋がり、ひいては若い人材の参入を促す好循環を生み出すことが期待されます。
DCAは、業界の課題解決と発展のため、具体的な組合活動を積極的に推進しています。

ここ2~3年で会員数が約10社増加し、さらに3社ほどの加入希望があるなど、DCAの活動への注目度と期待が高まっています。「まだ増やせる自信はなぜか。」という言葉は、組合の求心力の高まりを示唆しています。会員数が増えることで、業界全体の意見がまとまりやすくなり、政府や関連機関への発言力も増し、ひいては業界全体の地位向上に繋がります。
「賛助会員から買いましょうよ。必ず買いましょうよ。賛助会員以外のところから買わないでください。その上で1%いただきましょうよというのを私は強く促進して、担当委員にもこれを徹底しよう。」というルールは、組合の財政基盤を強化し、その収益を会員への還元や、業界全体のプロモーション活動、技能講習の充実などに充てることで、組合の価値をさらに高めることを目的としています。
技能審査試験の大幅値上げを実施したにもかかわらず受験者数が増加していることは、「業界の注目度が上がっている。」という発言の裏付けであり、ダイヤモンド工法の専門技術に対する社会的な評価と需要が高まっていることを示しています。これにより、技術者の質の維持・向上と、業界のプロフェッショナルとしての信頼性向上が図られます。
製造業におけるベテランの技術伝承の難しさを鑑み、DCAはDX技術を活用した教育補助ツールの導入を模索しています。例えば、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を用いたシミュレーション訓練、オンラインでの技能講習などが考えられます。これにより、新入社員が早期に戦力となるよう、より効率的かつ実践的な育成が可能になります。また、メーカー側には「ある一定のパフォーマンスがすぐできるもの」の開発を求めることで、誰でも扱いやすい機械の普及を促し、人材育成の負担を軽減しようとしています。
業界の認知度向上は、人材確保の喫緊の課題であり、DCAは多角的な広報活動を重視しています。SNS、特にInstagramのフォロワー数2032名という実績は、デジタルを活用した情報発信の重要性を示しています。

さらに、「解体キングダム」のようなテレビ番組との連携を通じて、一般の人々に業界の魅力を伝えるメディア活用も重要視されています。「もっともっとダイヤモンド工法が採用されるように広く、組合を利用していきたい」という目標は、単に人材を増やすだけでなく、ダイヤモンド工法の適用範囲を広げ、需要そのものを拡大しようとする意欲の表れです。
現場の映像を積極的に公開し、「こんな仕事があるんだっていうのを、工業高校の生徒を呼ぶことによって」と、次世代を担う学生を直接現場に招くことで、具体的な仕事内容への興味を喚起し、将来の担い手を育成する狙いがあります。また、これまで不足していた国土交通省などの関係機関への情報発信も強化し、業界への理解を深める努力がなされるべきとされています。
C&D JAPANは業界唯一の専門展示会であり、各社が新製品を発表する重要な機会として位置づけられています。「業界で唯一の専門の展示会なので参加できることに誇りをもっていますし、やはりそこに自信の商品を毎年展開したいな。」という言葉からは、この展示会が業界の技術力と発展を示す場であることが分かります。来場者数増加のため、単なる製品展示に留まらず、映像コンテンツの活用や、工業高校の生徒などの若い世代を積極的に招く企画が検討されています。
これは、業界への関心を高め、将来の就職先として選択肢に加えてもらうための重要な戦略です。将来的には、JCSDA(日本コンクリート切断穿孔業協会)との合同開催を通じて、「コマ数も倍に増やして、入場者数はまあ4桁。そのぐらいの規模のこと」を目指す壮大なビジョンも語られています。これは、「ダイヤモンド業界の展示会という名のお祭り」をイメージし、専門家だけでなく一般の人々にも開かれたイベントにすることで、業界の認知度と魅力を飛躍的に向上させたいという強い思いが込められています。

ゼネコンがカッターの世界で特許を取り始めているという言及は、業界の技術革新の加速と、それに伴う競争環境の変化を示唆しています。特に「斜め」の切断のようなニッチでありながら重要な技術領域で特許が取得され、「ほとんど参入できないんだ」という状況が生まれていることは、中小企業や新規参入者にとって大きな障壁となる可能性があります。これは、既存企業が独自の技術や特許を保有することの重要性を再認識させるとともに、技術開発競争が激化している現状を浮き彫りにしています。
「これだけの技術があるのに、なぜ世界に出ないのか。」という問いは、日本のダイヤモンド工法の技術力の高さに対する自信と、海外市場への大きな進出機会が潜在していることを示唆しています。日本の技術は、その精密さ、安全性、効率性において世界的に高い評価を受ける可能性を秘めており、国内市場の縮小が見込まれる中で、新たな成長の柱となり得ると考えられます。
現場で働く人々が「うるさいわね。汚いわねって言われて」モチベーションが下がる現状に対し、「我々が行っていることがライフラインを支えることでこの社会を支えているってことをもっとアピールすべきだ。」と、社会への貢献度を明確に伝えることの重要性が語られました。これは、単に賃金だけでなく、仕事への誇りや社会からの評価が、労働者の定着率向上や新たな人材の確保に繋がるという認識に基づいています。
機械の軽量化・高出力化が進めば、「女性が入ればまた1つ、それだけの労働人口が増えてくるはずです。」と、労働人口減少への対策としても女性の活躍に大きな期待が寄せられています。建設現場における女性の進出は、多様な視点や能力をもたらし、職場環境の改善にも寄与すると考えられています。
下村新体制になってから、議論が活発になり、「理事会に来たくなかった人が来たい。喋りたくなかった人が喋り終わんない。なんでそんな喋る?」という冗談めかした発言からも分かるように、参加意欲が飛躍的に高まっていることが強調されています。これは、組合員が自らの意見を自由に発信し、業界の未来について積極的に貢献しようとする意識の高まりを示しており、組合の結束力と実効性を高める上で非常に重要な変化です。
この座談会からは、ダイヤモンド工事業界が、人口減少による人手不足という喫緊かつ大きな課題に直面しながらも、その仕事の永続性と社会貢献性への強い確信を持っていることが明示されました。課題解決のためには、単なる労働力確保に留まらず、省力化・自動化の推進による生産性向上、適正な単価の確保による持続可能な経営基盤の構築、そして若い世代や女性を含めた多様な人材確保のための業界の認知度向上と魅力発信が不可欠です。
DCA(ダイヤモンド工事業協同組合)は、これらの課題に対し、組合員数の増加、購買手数料の厳格化による財政基盤強化、技能審査の強化を通じた技術者育成、広報活動の充実によるイメージアップ、そしてC&D JAPANの規模拡大などを通じて、業界全体の活性化と発展に積極的に貢献していく強い意志を示しています。特に、「奪い合う時代から分け合う時代」への転換という理念と、業界が一体となって適正な利益を確保していくという前向きな姿勢は、この困難な時代を乗り越え、業界がさらなる発展を遂げるための重要な原動力となることが期待されます。
